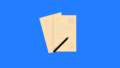近年、働き方改革が推進される中、「ウェルビーイング」という概念が広がりつつあるのをご存じでしょうか。
労働者が前向きに心身ともに健康的な状態で働けるよう、企業がよりよい組織運営を行うために必要な概念であると注目を集めています。
この記事では、ウェルビーイングの意味、今注目される理由、そしてウェルビーイングを導入することによるメリットについて解説していきます。
1. ウェルビーイングとは?
はじめに、「ウェルビーイング」の意味について見ていきましょう。
直訳すると、「幸福」「健康」「福利」という意味ですが、1946年に定められた「世界保健機関(WHO)憲章」の文中で、下記のようにウェルビーイングの概念が初めて言及されました。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
世界保健機関(WHO)憲章とは | 公益社団法人 日本WHO協会
健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。
そこからウェルビーイングは、単なる身体的な健康ではなく、精神的にも社会的にも健康であること。そして、その良好な健康状態が、瞬間的ではなく持続することを指す、新たな幸福の概念として世界中に広まりました。
2. 幸せを構成する5つの要素


よりよい生き方について科学的に研究する「ポジティブ心理学」を創設したアメリカの心理学者セリグマン博士は、ウェルビーイング・持続的な幸福の重要性を提唱。2011年の著書『Flourish:ポジティブ心理学の挑戦 “幸福”から“持続的幸福”へ』の中で、ウェルビーイングに基づいた幸福は、下記の要素(PERMA)で構築されていると書いています。
- Positive Feeling(ポジティブな感情):うれしい、楽しいなど前向きな感情
- Engagement(エンゲージメント):何かに没頭すること
- Relationship(関係性):友人・家族など、周囲の人々と本質的につながっていること
- Meaning(意味・意義):生きる意味、何のために生きているのか
- Achievement(達成):何かを成し遂げること、達成感
ちなみに、幸福度を数値化したものの一つとして毎年国連が発表する「世界幸福度ランキング」があり、こちらは下記の6要素を加味して順位付けされています。
- 1人当り国内総生産(GDP)
- 健康寿命
- 社会的支援
- 人生の自由度
- 他者への寛容さ
- 国への信頼度
2021年版では、153か国中、日本の順位は56位。先進国の中ではかなり低いところに位置しています。
しかし、そもそも政治や国民性などが全く異なる国ごとに、幸福の尺度を比較するのは難しいものです。また、セリグマン博士の調査によると、人生の満足度を質問された際、70%はその瞬間の気分に左右されてしまうというデータがあるそうです。
アンケートで幸福度を測ることは難しいものと言えますね。
3. ウェルビーイングが注目される理由
では、ウェルビーイングが今なぜ注目されているか、その理由を見ていきましょう。
ウェルビーイングは、そもそも社会福祉や医療関連分野で使用される専門用語でした。しかし、昨今の働き方改革や新型コロナウィルスの感染拡大による影響もあり、ビジネスシーンでもウェルビーイングの概念が重要な指標として考えられています。
その背景として、社会における価値観の多様化や労働人口の減少による人材確保の必要性が挙げられます。
若年層の人口減少により労働力不足が慢性化。現在のペースで少子高齢化が進めば、40年後の日本の労働人口は4割減少すると予測されており、より一層労働力の確保が難しくなっていくことが考えられます。
また、働き方や生き方の価値観が多様化する中、様々な考え方やワークスタイルにあわせ、自分らしく働くことができる仕事環境が求められています。新型コロナウィルスの感染拡大によるリモートワークの導入により、柔軟な働き方について多くの方が考えるきっかけとなったことも大きいと言えます。
そして、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標である「SDGs」の17項目のうちの一つとして、「すべての人に健康と福祉を」という項目が設けられていることでも、まさに今、ウェルビーイングの概念が必要とされていることがお分かりいただけると思います。
4. ビジネスでの導入事例~株式会社イトーキ
先述したように、労働力不足により人材確保が難しくなっていく中、各企業では他社との差別化を図り、人材の確保及び定着化を高める必要性が高まっています。
そのためには、ウェルビーイングの概念を組織運営に導入しよりよい職場環境作りが重要となります。
実際にウェルビーイングを導入した日本企業の事例を見てみましょう。
オフィス家具で有名な株式会社イトーキでは、2018年に新本社オフィス移転をきっかけに、新しい働き方を実現するためのオフィスデザインを体現した「ITOKI TOKYO XORK」を作りました。
コミュニケーションを活性化させるスペースづくりや、気持ちの切り替えを促すスペース、集中するための個別空間など、生産性を向上させる様々な工夫がされており、心身を健全に保つための空間品質基準「WELL Building Standard」のゴールドレベルも取得しています。
また、2017年には、社員の心身の健康を重要な健康課題ととらえ、戦略的に健康経営を推進するため「健康経営宣言」を制定。健康促進やメンタルヘルス、卒煙、運動推奨など、12の具体的な取り組みを定め、経営、健康保険組合、労働組合、社員、家族が一体となった健康づくりの推進を行っています。
参考: ITOKI TOKYO XORK
参考: 健康経営宣言 | ITOKI
5. ウェルビーイング導入のメリットとは


先ほどご紹介した株式会社イトーキの導入事例のように、ウェルビーイングの概念を導入する企業は増加しています。
ウェルビーイング導入のメリットとしては、社員の職場に対する満足度があがり、仕事の生産性が向上すること。そして、会社の業績アップにもつながる可能性があることが最も大きなメリットだと言えます。
また、職場の満足度が上がれば自ずと離職率も下がり、会社への愛着を持って長く働く社員が増えていくことで総合的な企業の力が高まります。企業の魅力が高まれば、外から優秀な人材を確保できるようにもなっていくといった好循環が生まれていきますよね。
このように、企業の健康経営を推進するには、ウェルビーイングの概念が必要不可欠と言えるのです。
6. まとめ
今回は、今注目のキーワード「ウェルビーイング」について、意味や導入事例、メリットについて見てきました。企業でのウェルビーイング概念の導入は、世界的にはスタンダードになりつつありますが、まだまだ日本では浸透しているとは言えない状況です。
個人としても企業、社会全体としても、ウェルビーイングの概念を取り入れていくことは、豊かな暮らしを実現するための近道と言えるでしょう。